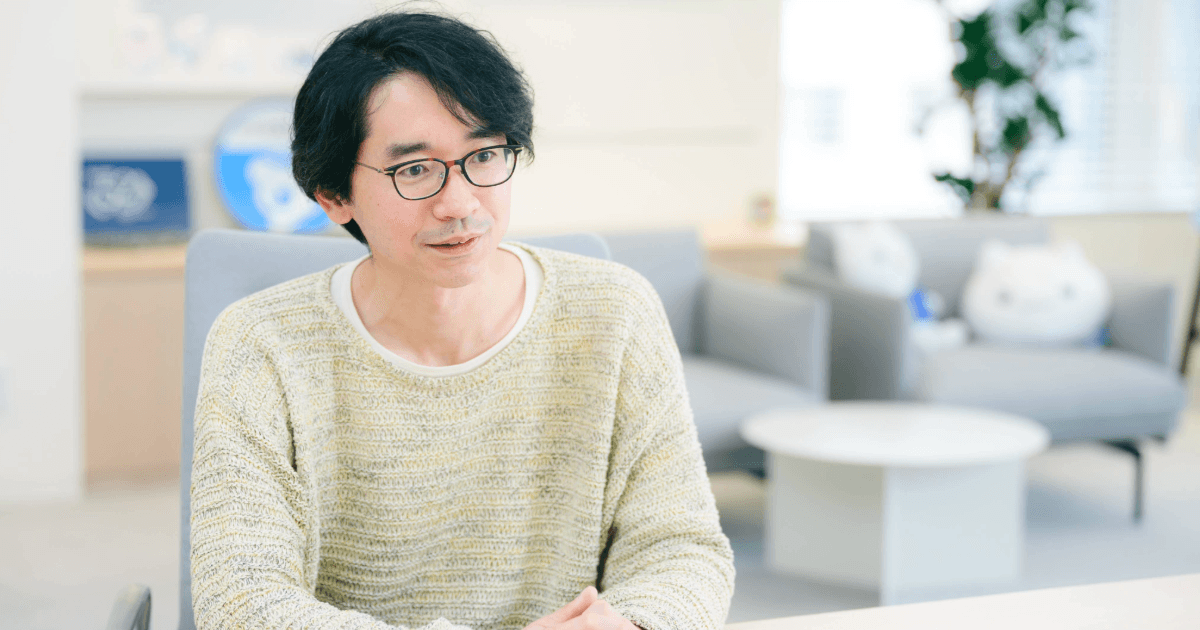AI記事要約
コロプラでは、グローバル市場への進出強化と新たな体験価値の創造を実現するため、「市場創造型マーケティングの実現」を目指し、2025年1月にマーケティング組織を再編しました。スマートフォンゲーム市場の成熟化や競合環境の激変により、従来の手法が通用しなくなった今、データだけでなく自らの感覚を信じた戦略立案と、制約を乗り越える柔軟な発想力が求められています。今回は、『白猫プロジェクト』『神魔狩りのツクヨミ』『アリス・ギア・アイギス』を担当する3人のマーケティングディレクターに、変化する市場でのマーケティング業務の具体的な内容や、業務のやりがい、そして求める人物像について語っていただきました。
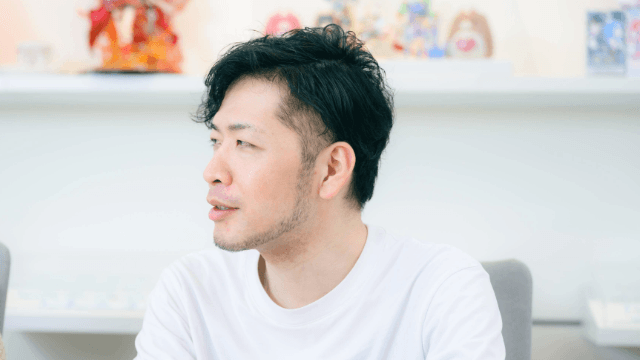
エンターテインメント本部 Bスタジオ 部長 マーケティングディレクター
- 藤野 貴之
家庭用ゲーム開発会社にデザイナーとして勤務。その後、起業、スマートフォンアプリ開発会社、外資系ゲーム開発会社を経て、2019年にコロプラへと入社。複数タイトルでディレクターやアートディレクターを担当した後、横断デザインスタジオ部長やマーケティング戦略部部長などを歴任。2025年2月より現職。

マーケティング戦略部 副部長 マーケティングディレクター
- 星野 公佑
複数の総合広告代理店で営業職を10年間務めた後、知人の紹介で2018年にコロプラへと入社。広告メディアのバイイング・出稿業務を担当した後、新作タイトルの企画や運用タイトルのプロモーションなどに携わる。現在は新作タイトル『神魔狩りのツクヨミ』のマーケティング・プロモーションに従事。
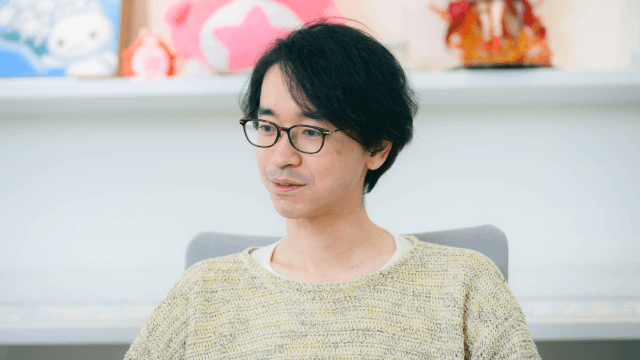
マーケティング戦略部 第2グループ マネージャー マーケティングディレクター
- Y.S.
大学を卒業後、新卒で総合広告代理店に入社。営業職として、アニメ・ゲーム業界のクライアントを担当する。10年ほど勤めた後、2019年にコロプラに入社。ユーザー目線での企画立案、施策の実施を軸に据え、『アリス・ギア・アイギス』や新作タイトル『異世界∞異世界』を担当中。
難化する市場環境、変化するマーケティングの役割
2025年1月、マーケティング組織を再編したそうですね。

そうなんです。コロプラはこれから、ミッション、ビジョン、中期経営計画に基づき、グローバル市場への進出強化と新たな体験価値の創造を叶えるために、「市場創造型マーケティングの実現」を目指していきます。その目標を達成するため、2025年1月、マーケティング組織の再編を行いました。僕の所属するエンターテインメント本部Bスタジオでは、『白猫プロジェクト』や『フェスバ+』といった自社開発IPの運用におけるマーケティング、プロモーション、顧客満足度向上に向けた施策などを担当。Y.S.さんや星野さんの所属するマーケティング戦略室では、主に新作タイトルのマーケティングや、数年後にリリースを目指すタイトルの企画開発の部分を手がけています。
マーケティング部門に求められる役割が大きく変化しているとのお話ですが、皆さんは日々の業務の中で、そうした変化は実感していますか?

そうですね。少しずつですが、変化していっているなと感じています。

最近強く思うのが、「一昔前に有効だった手法が、現在はことごとく通用しなくなっている」ということです。例えば、私が入社した頃は、コロプラもテレビCMを次々と仕掛けている時代でした。しかし、現在はそうした仕事はほとんどありません。テレビCMを打ってマスのユーザー層を獲得するという施策が、あまり効果を上げられなくなっているからです。「個人の時代」「多様性の時代」と言われて久しいですが、価値観や趣味嗜好の細分化が極限まで進んだのが現在の社会だと感じています。

SNSを含むWebのレコメンドフィルターの精度が圧倒的に良くなっているのも影響していますよね。最近は、SNSで気になる投稿を見ると、その直後から「あなたへのおすすめ」で画面が埋め尽くされますから。そういった環境下にある消費者に、何か新しい情報を届けようと思っても、なかなか届かない時代にあるんです。

市場の変化も激しいですよね。特に国内のスマートフォンゲーム市場は、成熟フェーズにあります。長く人気を博しているタイトルのパワーが強く、新作の参入障壁が上がっており、新しいタイトルが大勢のユーザーさまから支持を集めることが非常に難しくなっています。加えて、競合環境にも大きな変化がありました。昨今は中華圏企業の存在感が増しており、スマートフォンの買い替え頻度が長期化していることも影響して、なかなか新規のスマートフォンゲームを触っていただくことが難しい状況にあります。

最近のスマホタイトルは容量も大型化しており、ヒット作品には、アプリの容量が非常に大きいものが多い。だから、スマートフォンのデータ容量の空きがほとんどないために、他のゲームに手を出さない人も増えています。

それでも、10年前のように、スマートフォンを2〜3年に1度は買い換える時代なら新作が入り込む余地はありました。しかし、最近は各機種の性能と価格が上がっていることから、多くの方が現在使用している端末を長く使う傾向にあります。ゲームアプリの新陳代謝が起きづらくなっているのも、我々がマーケティングのあり方や戦い方を変えなければならない理由のひとつです。

中華圏企業の広告出稿額が桁違いなのも大きいですね。普通に戦ってもこちらが負けてしまうので、新たな角度から工夫を加えて、ゲームのマーケティングに向き合っていかなければならないと感じています。
非常に難しい市場環境にあるのですね。そうした中で、新たな体験価値の創出、市場創造を目指すのはとても難易度の高いことのように思いますが、皆さんは日頃どのような取り組み方をしているのですか?

新しい体験について考える際は、あらゆる制約条件を取り払い、まずは自由に発想するのを大切にしています。

僕は最近、データをあまり信用しすぎないように気をつけていますね。市場環境や消費者が大きく変化しているからこそ、自分の中にある「これはおもしろい」「これならユーザーニーズを満たせるのではないか」という感覚をより一層研ぎ澄まし、それを信用するようにしています。

分かる。“勘”ではなくて、“感覚”なんだよね。僕も日頃の仕事の中で、感覚を大切にすることは多いですね。この“感覚”がどこから来ているかというと、今まで自分が見聞きしたり、経験したりしてきたことから出てきているんです。だからこそ、それを信じる意味は大きいというか。

逆に感覚が働かないということは、経験やインプットが不足しているということ。ひとつのバロメーターになりますよね。
興味深い話ですね。皆さんが日頃どのようなところからインプットしているのかも気になりました。

ゲームや映画、音楽などのエンタメからビジネス、芸能ゴシップまで、あらゆるニュースを一度斜め読みするようにしています。その中で気になるトピックを掘り下げて読み、場合によっては書籍にあたることもあります。現代人の感情や心の動きが知りたいので、炎上ネタなども、怒りの源泉やその背景に何があるのか、といった視点で観察したりします。

僕は『異世界∞異世界』というアニメに絡むタイトルを手がけているので、Xを中心にSNSで情報収集を行っています。アニメ界隈で流行っている情報をチェックしつつ、その源流がどこにあるのかを探ることを、日々意識しています。

僕は星野さんに近いスタンスで、ChatGPTを活用してニュースを確認しています。ChatGPTに「ここ2週間で日本で話題になったニュースを、なぜ話題になったのかの考察も含めてまとめて」と指示を出すと、情報を瞬時にリストアップしてくれるんですよ。その中で気になるネタをさらに深掘りしたり、深く知るための情報源をさらにChatGPTで調べたりして、情報を得ています。
新作タイトルのマーケティング業務に迫る
新規開発タイトルのマーケティングについて伺いたいです。星野さんは『神魔狩りのツクヨミ』で、どのようなミッションのもとに施策を進めたのか、可能な限りお話いただけますか?

『神魔狩りのツクヨミ(以下、『神ツク』)』は、これまで数々の名作を手がけてきたゲームクリエイターの金子一馬さん(2023年コロプラ所属)が世界観の設計やキャラクターデザインに携わった、ローグライクジャンルの新作ゲームです。このプロジェクトの目的の一つは、「画像生成AIを組み込んだプロダクトを、市場やユーザーさまに受け入れていただける状況をつくる」ということでした。生成AIは現在、ゲーム開発への活用に賛否両論が沸き起こっています。人によって考え方が大きく異なり、個々の解釈や価値観、置かれている状況などとも結びついているため、従来の宣伝・プロモーションのやり方では、炎上に発展し、大きく拒絶される可能性があると考えました。ただ、生成AIを活用したゲームの開発は、今後のゲーム業界の発展を考えれば、今取り組むべきチャレンジです。現時点では、生成AIに興味があり、金子さんの過去作やローグライクゲームが好きな方々にのみ情報を届ける必要があると考え、プロモーション計画を設計していきました。

加えて、金子さんのイラストのファンの方々にも、できる限り手に取っていただきたいという狙いもあったんですよね。

そうなんです。今作は金子さんが久しぶりに手がけられる完全新作。しかもそれが、スマートフォンゲームであること、生成AIを組み込んでいること、ローグライクゲームであること……など、これまでの金子作品と比べると、異なるポイントが多数あります。ファンの方々に『神ツク』をプレイしていただくためには、金子さんが新たな挑戦に取り組む理由や考え方などを、余すところなくお伝えする必要があると考えました。そこで、金子さんへのインタビュー記事を各種メディアに取り上げてもらったり、配信動画やオウンドメディアなどの表現を細かく入念に作り込んだりと、ファンの方々に納得していただくためのさまざまな施策を実施。その結果、金子さんがこれまでファンの方々と構築してきた信頼関係も相まって、多くの金子さんファンの皆さまに『神ツク』のチャレンジを受け入れていただくことができました。

コロプラとして伝えたかったことが、しっかりと伝わった手応えがありました。想いやコンセプトを世の中に正しく伝えられた理由のひとつとして、星野さんが構成や脚本づくりに携わったプロモーションビデオ(PV)も大きかったのではないかと思います。ゲーム内における生成AIの位置づけをしっかりと説明しつつ、金子さんの完全新作であることが伝わるような、ファンの方々に期待感を持っていただけるような映像を星野さんが作り上げてくれたんです。
「project MASK」アナウンストレーラー

PVの構成からコンテまでを全て自分の手で作成するのは初めての作業だったのですが、金子さんの作品らしさを表現しつつ、抽象的な概念を3分程度の動画の中で魅力的に伝えるということにはすごくこだわりました。特に生成AIの要素がゲーム内で果たす役割と現実世界での位置づけを的確に説明することが難しくて、一時はPV上で伝える事を諦めそうになったこともあるのですが、セリフやナレーションを何度も書き直して、ようやく完成したのがあの映像です。

金子さんにコンテを確認してもらう時は、めちゃくちゃ緊張したよね。

あの瞬間は本当にドキドキしましたね……(笑)。コンテ案の作成も大変だったのですが、それ以上に、いざ映像として編集を始めてみると、コンテ時にイメージしていたような印象の動画に全くならなくて、その時期はかなりつらかったです。でも、無事に映像を完成させることができて、本当に安心しました。

「ファンを巻き込むマーケティング」とは?
Y.S.さんは、『アリス・ギア・アイギス』の担当だと伺っています。このタイトルでは、どのような方針でマーケティングを行っているのですか?

『アリス・ギア・アイギス』は、コロプラが携わっているゲームの中でもトップクラスにユーザーさまとの距離が近いタイトルだと感じています。そのため、プロモーションなどを行う上では、「ユーザーさまと一緒にタイトルを盛り上げること」を常に意識しています。時には、Xでの発信がユーザーさまとの“夫婦漫才”のようになってきていて。ユーザーさまが求めるものを把握した上で、その斜め上を行く企画を考えられるように心がけていますね。とはいえ、時に振り切りすぎて、ユーザーさまを置いて行ってしまうケースもあるのですが……(笑)。

“夫婦漫才”は言い得て妙だと思います。少し不思議な内容でSNSに投稿したとしても、ファンの皆さまが「アリス・ギアだしな」と納得して、楽しんでくださるんですよ。そして、我々の企画や発想を存分におもしろがってくださる。以前もあるイベントの発表で、4時間の焚火動画を配信したのですが、ユーザーさまがSNSなどで「こんなに長いティザーってある?」「どんな告知だよ!」とツッコミを入れてくださって、とても盛り上がりました。「次はどんな企画だろう?」とお互いに楽しみ合っているような、そんな関係値をユーザーさまと築けている、稀有なタイトルだと思います。
ユーザーさまを巻き込みながら、とことん楽しませるようなマーケティングのあり方は、コロプラとしても大切にしていきたいところなのでしょうか。

各タイトルの置かれた市場環境なども影響しますから、すべての作品に『アリス・ギア・アイギス』のようなマーケティング施策が通用するわけではありません。ですが、コロプラとして「Entertainment in Real Life」と掲げている以上は、やはりどのタイトルも最終的に「ユーザーさまにいかに楽しんでいただけるか」という部分を目指していくのは、変わらない方針だと考えています。
藤野さんは『白猫プロジェクト』を担当されているそうですが、10年続く長期タイトルのマーケティングでは、どのようなことを大切にされているのでしょうか。

歴史と現状を振り返った上で、「こうありたい」という未来像を描くことですね。タイトルを長く愛してくださっているファンの皆さまが何を求めているのかを理解し、その上で、定性的にも定量的にも目指すべき状態を定め、そこに向けたマイルストーンを切ることを普段から行っています。特に『白猫プロジェクト』は、コロプラを代表するタイトル。コロプラのイメージを左右する“看板”のような作品となっていますから、『白猫プロジェクト』を引き続き盛り上げていけるように、現在やるべきこと、未来に向けてやるべきことを整理し、実行しています。
ここまでお話を伺ってきて、コロプラのマーケティング職は、担える仕事や実行できる打ち手が非常に幅広いのだなと感じました。

そうかもしれません。『神ツク』は、僕が経験した中でも特に携われる範囲の広いプロジェクトでした。僕は今回、マーケティング計画の方針策定はもちろん、コミュニケーションコンセプトの設計やプロモーション施策のプランニング、広告クリエイティブのディレクション、広報PR活動の部分にまで携わっています。前職の広告代理店で例えるなら、ストラテジックプランナーやクリエイティブディレクター、メディアプランナー、営業責任者の仕事に関わることができたんです。コロプラでは、自分次第でいくらでもやりたいことに挑戦できます。

挑戦に寛容な風土がありますからね。

「やりたい」と手を挙げたら、みんながおもしろがってついてきてくれる環境がありますよね。

担当プロジェクトの中で、自分が何の役割を、どこまで担うのか、本当に自分の匙加減で決められるので、日々おもしろさを感じながら仕事をしています。

「製販一体型のプロジェクトが増えていく」 これからのコロプラに参画する醍醐味
マーケティング部門の組織の雰囲気を教えてください。

基本的にプロジェクトごとに動くことが多いため、各プロジェクトでそれぞれ違った雰囲気がありますが、マーケティング戦略室は20~30代のメンバーが多いため、時に学生ノリも混じりながら、楽しく仕事をしています。

いい意味でうるさいですよね(笑)。

『白猫プロジェクト』のマーケチームも当てはまるかもしれない(笑)。

マーケティング業務の性質上、人との会話の中で発想が生まれることも多いので、他の部署と比べても雑談の頻度は多いと思います。

話すことが好きな人たちだからこそ、マーケティング職に就いているという側面もあるよね(笑)。
マネージャーとしてチームを率いる上で大切にしていることはありますか?

私の場合、その方の入社年次やポジションに関係なく「限界まで自力で考えてもらう」というのは、かなり大切にしている部分だと思います。目の前の課題に対して、自ら考え、自分なりの答えを見つけてもらうこと。あとは、その人の得意領域や成長へのステップ、伸びしろを考慮しながら、適任だと思った仕事を振っていくことでしょうか。チームメンバーには、ゲーム開発において「タイトルの魅力を社会に伝える責任者は自分たちだ」という自覚を持ち、開発チームとも対等に意見を交わし合えるマーケターになってほしいと思っています。

「信じて任せる」ということですね。途中で手や口を出すことなく、その方がやろうとしていることを一度やり切ってもらうということを意識しています。

僕は個々人の意志や意向を確認し、それに適した業務をアサインしていくことを大切にしています。仕事に対する想いや考え方、プライベートの事情は人それぞれ。その人に合った仕事の仕方を実現し、力を発揮してもらえるように日々考えながらマネジメントと向き合っています。
マーケティングチームのメンバーとして、どのような方に仲間として加わってほしいですか?

逆境に強く、高い視座を持っていて、視野が広い方でしょうか。あとは、自分自身を常に俯瞰して疑えること。人は物事の見方が偏ってしまいやすいものですが、この仕事をしていると、自分の視野が狭くなっていないかを定期的に確認することが大切だと感じます。また、課された制約の前にへこたれず、「なかなかおもしろいお題が来たな」とポジティブな挑戦として受け止められることも、コロプラのマーケティングに携わる上で欠かせないメンタリティだと思っています。

そうですね。いろいろな制約の中で物事を動かさなくてはならない場面も多々ありますから、目の前の前提条件を理解しつつも、その上で「自分のやりたいこと」を掲げて行動できる人が活躍している印象があります。意志や想いがあれば、制約を乗り越え、もう一段高い視座で物事を決断できます。そういう人は、仕事を目一杯楽しんでいる印象があります。

加えて、柔軟に方向転換ができることも重要です。自分の責任の下にさまざまな意思決定をし、それを実行に移したとしても、必ずしも上手くいくとは限りません。やりたいことを実現してみて、上手くいかなかったら、新たな仮説を立てて、時にドラスティックに方向性を変えてみる。そうした仮説検証のサイクルを常に回すような、ある意味で研究者気質のある方はコロプラのマーケティング業務にマッチしているように思います。
最後に、担当業務やチームの今後の展望をお聞かせください。

新規タイトルの開発では、会社として「顕在化していないニーズの掘り起こし」に挑戦しています。市場にいるお客様自身がまだ気づいていないニーズを把握し、それに応えられるようなゲームを届け、生活をより楽しく、素晴らしいものにしていくというのが、我々の使命だと捉えているので、それを体現できるチームにしていきたいです。理想を言えば、新市場の掘り起こしや全く新しい体験の創出を高い打率で実現できるようなチームが作れたら。そのためにも、引き続き日々の業務に邁進していきたいです。

コロプラのゲームは、新旧すべてのタイトルを含めて、やはりユーザーさまがいらっしゃるからこそ運営やリリースが叶っています。だからこそ、僕としては、常にユーザーさまを主語に物事を語りたい。ユーザーファーストであることが前提として成り立っているようなチームであれるように、引き続き尽力したいと考えています。ユーザー目線を持って仕事をするためには、冒頭でお話したとおり、データだけでなく、感覚を研ぎ澄ませて社会の声を集めることが欠かせません。目の前の数字だけにとらわれるのではなく、自分の感覚や感性を信じて、ユーザーさまと対話ができるようなマーケティング組織にしていきたいなと思います。

僕は、マーケティング組織も含めて、会社全体で「おもしろいゲームを作るために、業務や部署の垣根を超えて取り組みを推進できる組織」でありたいし、そうしていきたいと思っています。星野さんが携わっている『神魔狩りのツクヨミ』では、開発者がプロモーションに携わり、マーケティング担当者も開発に携わって、お互いに意見を出し合いながら、より魅力的なゲームを作ることに貢献していました。難しい市場環境にあるからこそ、そういった製販一体型のプロジェクトのあり方を会社全体で目指していきたい。それができた先に、ファン層の拡大や会社の成長があるのだと思います。今後、「作る」と「届ける」をもっと密接に連携させたプロジェクトが増えていきます。「新しいゲーム体験を作り、届けたい」と考えている方には、挑戦しがいのある環境が待っていると思います。