.png%3Fw%3D800&w=3840&q=90)
AI記事要約
『フェスバ+』とは?
『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』や『モンスターストライク』(MIXI)など、人気ゲームのキャラクターたちが作品の垣根を越えて集結するパーティロイヤルゲーム。プレイヤーは個性豊かなキャラクターを操作し、仲間と連携しながら爽快なバトルを繰り広げる。
技術に裏打ちされた快適な操作性と公平な対戦環境に加え、プレイヤーとしてだけでなく、他者のプレイを応援して楽しめる「視聴・配信機能」も搭載。遊んでも、観ても楽しい、新しいエンターテインメント体験を提供する。

テクノロジー推進部本部 第2技術開発部 部長
- 阿部 大祐
2013年にコロプラへ中途入社。『白猫テニス』『プロ野球バーサス』など、数々の新規タイトルの開発に携わる。特にマルチ対戦ゲームのプロジェクトに関わることが多い。『フェスバ+』では、プロジェクトの立ち上げからプレイングマネージャーとして参画し、バトルシステムや視聴配信機能の実装からリリース管理まで、幅広く担当している。
「好き」を仕事に。格闘ゲームへの情熱が導いた開発者の道
まず、阿部さんがゲーム開発の道に進まれたきっかけを教えてください。
高校卒業を控えて進路を考えたとき、将来どんな仕事をしたいか、自分なりに真剣に考えました。そのとき、ごく自然に「やっぱり好きなことを仕事にしたい」という結論に至ったんです。そして、僕にとっての「好き」は、昔も今も変わらずゲームでした。その一心で、ゲーム開発を学べる専門学校の門を叩きました。
数ある職種の中から、プログラマーを選ばれたのはなぜでしょうか。
実は消去法なんです。ゲーム開発には様々な役割がありますが、例えば絵を描くのは昔から本当に苦手で。プランナーのように面白い企画を考えるのも、自分には向いていないと感じていました。一方で、PCに触ること自体は好きでしたし、一つのことを突き詰めて調べる、いわゆる「ゲーマー気質」な探究心は持っている自覚がありました。
最初はプログラミングも「難しいな」と感じることばかりでしたが、勉強を進めるうちに、複雑なロジックが自分の書いたコードで思い通りに動いた瞬間の面白さに気づいたんです。まるで難解なパズルを解き明かすような感覚でした。この「面白い」という感覚が、プログラマーとしての道を歩む大きな後押しになりましたね。
ゲームへの情熱が、プログラマーという仕事の面白さに繋がったのですね。特に思い出深いゲームはありますか?
やはり『GUILTY GEAR(ギルティギア)』シリーズですね。僕の人生を良い意味で狂わせたゲームです。もともと北海道出身なんですが、上京して一番驚いたのがゲームセンターの多さと、そこに集うプレイヤーたちの熱量でした。当時、新宿にあった格闘ゲームプレイヤーの聖地とも言えるゲームセンターに初めて足を踏み入れたとき、そのあまりのレベルの高さに衝撃を受けました。「これは本腰を入れて修行しないとダメだ」と、そこからは学業の傍ら、食費を削ってゲームセンターに通い詰める日々でした。
そこまで熱中された『ギルティギア』の魅力とは何だったのでしょうか。その経験は、現在の開発姿勢にもつながっているのでしょうか。
空中ダッシュや空中ガードといった、キャラクターを三次元的に、そしてスピーディーに操作できる自由度の高いアクション性ですね。もともとアクションゲームが好きだったこともあり、自分の手でキャラクターを意のままに操り、コンマ数秒の駆け引きを制する感覚に完全に魅了されました。当時のゲームセンターの大会は300人くらい集まって、歩く場所もないほど盛り上がっていて、あの独特の熱気は今でも忘れられません。そうした体験が今回の開発テーマにもどこか通じているのかもしれません。
前例がないなら、自分たちが作る
CEDECで明かされた挑戦の裏側
今回、CEDECでは『フェスバ+』のネットコードについて講演されました。このテーマを選ばれた理由を教えてください。
この技術を用いた大規模開発事例が見つからなかったため、少しでも情報として貢献できればと思ったからです
「Netcode for Entities」はUnity社が公式に提供しているネットコード(通信同期)のためのライブラリなのですが、僕たちが開発を始めた当時は、まだExperimental(実験的)なバージョンでした。使い方のドキュメントはあるものの、実際にリリースされたゲーム、特に『フェスバ+』のような規模の運用型タイトルでの採用事例が世界中どこを探しても見当たらなかったんです。
用語解説: Netcode for Entities
Unityが公式に提供する、オンラインマルチプレイゲームのための通信(ネットコード)ライブラリ。データを効率的に処理するアーキテクチャ「ECS (Entity Component System)」をベースに設計されているのが特徴。
プレイヤーの入力を予測して遅延を感じさせない「ロールバックネットコード」にも対応しており、アクション性の高い対戦ゲームにおいて、快適な操作レスポンスと公平なプレイ環境を実現するために重要な役割を担う。
だからこそ、「これだけの規模のゲームで、この新しい技術をどう使いこなし、プロダクトとして形にしたか」という僕たちの挑戦の記録を発表することに大きな価値があると考えました。
講演の準備で、特に苦労された点はありますか?
人前で話すのが苦手なので、準備はすべてが大変でした。特に資料作成は、膨大な開発の歴史を60分という限られた時間で、かつ分かりやすく伝えるために、構成から表現まで練りに練りました。
まず、プロジェクトの長い歴史の中で「この問題はいつ、どうして起きたのか」「なぜこの決断をしたのか」という事実を、過去の資料を漁りながら一つひとつ正確に掘り起こしていく作業に多くの時間を費やしました。そうして集まった情報を並べてみると、今度は話したいことが多すぎて、とても尺に収まらない。そこから「何を伝え、何を削るか」という苦渋の取捨選択が始まりました。
その甲斐あって、当日は非常に分かりやすく、流暢な講演だったと評判でした。
ありがとうございます。実は、完成したスライドを使って、会社の防音室に一人でこもり、本番さながらのプレゼン練習を10回以上繰り返したんです。最初は時間を大幅にオーバーしてしまい、そこからスライドを10枚以上削ったり、話すスピードを調整したりと、試行錯誤の連続でした。練習のしすぎで、本番前日には声がガラガラになってしまったほどです。ですが、その地道な準備があったからこそ、当日は落ち着いて話すことができたのだと思います。
当日の反響はいかがでしたか?
想像以上に多くの方に聴きに来ていただけて、とても手応えを感じました。講演後に設けられている「Ask the Speaker」という、登壇者に直接質問できる時間があるのですが、そこでもUnityさんや、同じく対戦ゲームを開発されている会社の方々から「なぜこの技術を?」「開発は大変じゃなかった?」と、多くの質問をいただきました。業界内でもこの技術への関心が非常に高いことを肌で感じることができ、自分たちのやってきたことは間違っていなかったんだなと、とても嬉しくなりましたね。


「情報がない」から始まった、手探りのベストプラクティス模索
前例のない技術への挑戦、開発現場ではどのような困難がありましたか?
やはり「とにかく情報がない」という点に尽きます。何か問題が起きても、どう実装するのが正解なのか、誰も知らない。ネットで検索しても、個人のブログで紹介されている小規模なサンプルくらいしか出てこない。僕たちはもっと大きなものを作ろうとしているのに、「このやり方で本当に合っているのか?」「大規模なデータになった時に破綻しないか?」という不安は常につきまといました。
かっこよく言えば、自分たちがベストプラクティスを作っている感覚でしたね。「誰もやったことがないなら、自分たちが最初の事例になる」。そのフロンティア精神で、とにかく「やろうとしていることはちゃんと動いているから、きっと合っているはずだ」と信じて、一歩一歩進んでいくしかありませんでした。
リリース後、ユーザーさんの反応で苦労された点はありましたか?
ネットワーク対戦の仕組み自体は、今のプレイヤーさんにとっては当たり前のクオリティが求められるので、良くも悪くも「何も言われなかった」のが答えかなと思っています。「通信がラグい」という声もなければ、「すごくサク-サクだ」という声もない。これは、プレイヤーが違和感なく遊べている証拠だと、ポジティブに捉えています。
一方で、パフォーマンスの最適化は常に課題としてありました。特にデバイスのスペックによっては、ネットコードの予測処理が大きな負荷となり、安定したプレイフィールを維持するために継続的な改善が必要でした。予測処理はゲームの根幹なので外すことはできず、現在もより幅広い環境で快適に遊んでいただけるよう、改善に取り組んでいます。
『フェスバ+』ではDGS(専用ゲームサーバー)を導入されていますが、これは大きなメリットがありましたか?
はい、非常に大きなメリットがありました。多くのスマホゲームで採用されているリッスンサーバー方式だと、誰か一人のプレイヤーがホスト(親機)になります。そのホストが通信を切断してしまうと、ゲームが中断されたり、他のプレイヤーがCPU(コンピュータが操作するプレイヤー)に切り替わったりしてしまいます。
『フェスバ+』ではDGSを導入したことで、サーバーが落ちない限り、誰か一人のプレイヤーが離脱してもゲームは継続されます。これにより、「ホストが抜けてルームから追い出された」といったストレスがなくなり、安定した対戦環境を提供できています。
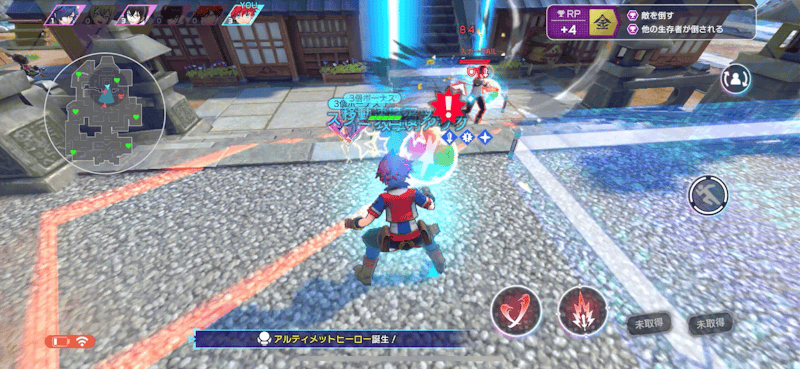
体験の根幹を支える技術
ネットコードが実現した「爽快感」と「公平性」
技術的な挑戦の先にある、『フェスバ+』の魅力についてお聞かせください。プレイヤーに一番体験してほしいのはどんなところですか?
やはり、こだわって作った対戦の「爽快感」ですね。僕が好きな「赤髪のヒーロー」というキャラクターがいるのですが、彼の必殺技は相手を脳天から地面に叩きつける、すごくパワフルな技なんです。その一撃で相手を弾き飛ばした瞬間は、最高に気持ちいいですよ。こうした一瞬の気持ちよさを、快適なレスポンスでぜひ味わってほしいです。
その爽快感を支えているのが、先ほどお話しいただいたネットコード技術による「公平性」ですね。
まさにその通りです。例えば、フィールド上のアイテムを2人のプレイヤーが同時に取ろうとしたとき、それぞれの画面では「自分が取った!」と思っていても、サーバーが「プレイヤーAの方が0.01秒早かった」と判定すれば、それが絶対的な結果になります。攻撃が同時に当たってどちらが倒れたか、という判定もすべて同じです。
DGSと「Netcode for Entities」を採用したことで、こうした結果の齟齬が一切生まれなくなりました。プレイヤーは純粋に自分の腕前と戦略で競い合うことができる。この「『当たり前の公平性』を、技術でしっかりと担保できた」ことが、このゲームの大きな魅力になっていると思います。
キャラクターの個性や戦略性という点ではいかがでしょうか。
そこもこだわったポイントです。『フェスバ+』には様々な個性を持ったキャラクターが登場しますが、それぞれの魅力を活かしつつ、戦略的な駆け引きが楽しめるように試行錯誤を重ねています。そんな中で「このキャラクターは強いけど、ちゃんと対策すれば勝てる」といった声を見かけると、とても嬉しくなりますね。キャラクターの組み合わせや戦況に応じた立ち回りなど、奥深い戦略性を楽しんでほしいです。


開発者視点で「ここも見てほしい!」というポイントはありますか?
技術的な部分で言えば、やはり「ネットワーク対戦の安定性」ですね。ユーザーの皆さんには意識させないのが一番なのですが、裏側では膨大な通信処理が動いています。それを感じさせないくらいスムーズな体験を提供できている点は、開発者として誇りに思う部分です。
また、「視聴・配信機能」も、このゲームならではの挑戦です。これは単なる観戦モードではなく、視聴者がコメントやギフトで試合に介入し、プレイヤーと一体となって盛り上がれる新しい遊び方の提案でもあります。自分がプレイしていなくても、応援するチームが勝てば一緒に喜べる。こうしたコミュニティ全体の熱量も、『フェスバ+』が目指した新しいエンターテインメントの形です。ぜひ、プレイするだけでなく、他のプレイヤーの熱い戦いも覗いてみてほしいですね。


人事を尽くした確信が、チームを前に進めた
前例のない技術への挑戦は、チーム開発においても大変だったと思います。特に意識したことはありますか?
エンジニアリングマネージャーとして、チームが常に前を向けるような雰囲気作りを一番に意識しました。未知の技術に挑戦するわけですから、メンバーが不安になるのも当然です。「本当にこの技術で大丈夫なんですか?」「Unityがサポートを打ち切ったらどうするんですか?」といった声も実際にありました。
そういう時でも、ただ精神論で「大丈夫だ」と言うのではなく、「きっと道は拓けるはずだ」と、チームを鼓舞し続けました。
そのポジティブさ、確信はどこから生まれてきたのでしょうか。
もちろん、ただ楽観的だったわけではありません。技術者として、やれるだけの準備とリスクヘッジは徹底しました。万が一、Unityのサポートが打ち切られたり、開発が頓挫した場合の代替案は常に想定していましたし、最悪の場合はオープンソースであるコードを自分たちで解析・改修する覚悟もありました。
「人事を尽くして天命を待つ」ではありませんが、「『やれることはすべてやった』という自負があったからこそ、『だから、きっとうまくいく』と強く信じることができた」んです。その確信が、僕自身のポジティブさの源泉であり、チームを前に進める原動力になったのだと思います。
今回の挑戦は、コロプラだからこそ実現できたと感じる部分はありますか?
それは間違いなくあります。コロプラには「現場に任せてくれる」という社風が根付いているんです。今回のネットコードの件も、視聴配信機能をゲーム内に実装するという前衛的な試みも、僕たちが「こういう技術で、これならいけるはずです」と提案したモック(試作品)を、会社がきちんと評価し、「じゃあ、あとは任せるね」と現場の裁量を尊重してくれました。
この「挑戦を後押ししてくれる文化と、僕たちの『やり遂げる』という意志が共鳴した」からこそ、この大きな挑戦が可能になったのだと感じています。
コロプラという環境、そして求める仲間
阿部さんが感じる、コロプラで働く魅力やメリットについて教えてください。
穏やかで真面目な人が多いことですね。ゲーム業界での経験も長くなりましたが、開発現場では時に熱意がぶつかり合うこともあります。その中でコロプラに来て印象的だったのは、社内の雰囲気の穏やかさです。もちろん、ものづくりに対する熱い議論は交わされますが、それが感情的な対立になることはなく、「誰もがプロフェッショナルとして互いに敬意を払って対話する文化」が根付いています。だからこそ、みんな落ち着いていて、建設的な議論ができるのだと感じます。
また、プロジェクト間の壁が低いのも大きな魅力です。オフィスに物理的な壁がないのもそうですが、例えば隣のプロジェクトで面白そうな技術を使っていたら、気軽に話を聞きに行けるんです。この風通しの良さは、エンジニアにとって非常に良い環境だと思います。
そんなコロプラで、阿部さんはどんな方と一緒に働きたいですか?
まず大前提として、ゲームやエンターテインメントが好きな人ですね。その上で、やはり前向きでポジティブな人と一緒に働きたいです。
ゲーム開発は、トライアンドエラーの連続です。特に新しいことに挑戦すれば、必ず壁にぶつかります。そんな中でも、「どうすればもっと面白くなるか」「この課題をどう乗り越えようか」と、楽しみながら手を動かせる人。そして、「面白いものを作るためなら挑戦を厭わない姿勢」を持っている人。そういう熱意のある方と、ぜひ一緒に面白いものづくりをしていきたいです。
未来へ。挑戦はまだ終わらない
この「Netcode for Entities」という技術は、今後どのように進化していくと思いますか?
Unityが公式でサポートしていくことで、モバイルタイトルも含めて、対戦ゲーム開発における当たり前の選択肢の一つになっていくと思います。これまでは有料のライブラリを使うか、自社で開発するしかなかったところに、無料でオープンソースという強力な選択肢が生まれた。これにより、開発者の裾野が広がり、より多様な対戦ゲームが生まれてくるんじゃないかと期待しています。
また直近では、『フェスバ+』初の公式大会『フェスバ+グランドチャンピオンシップ(FGCS)』が開催されていまして、オンラインでの予選を経て、9月7日にリアル会場で決勝戦が行われます。会場観戦はありがたいことに満員御礼となってしまったのですが、オンライン配信もありますので、興味のある方はぜひ画面越しに一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。対戦ゲームだからこそ、こうした大会で熱い戦いが見られるのも醍醐味の一つですし、この技術の可能性をさらに追求していきたいですね。

この技術を使って、次に挑戦してみたいことはありますか?
やはりPVP(対人対戦)ゲームですね。個人的には、10対10対10のような、ものすごい人数のプレイヤーが入り乱れて戦うゲームを作ってみたいです。この技術のポテンシャルがどこまであるのか、その限界を見てみたいという技術者としての探究心があります。
最後に、この記事を読んでいる方々へメッセージをお願いします。
ゲーム開発者の方、特にこれから対戦ゲームを作ろうとしている若いエンジニアの方には、僕たちのこの事例が少しでも参考になれば嬉しいです。ドキュメントも充実してきているので、ぜひこの技術を使って、新しいゲーム作りに挑戦してみてください。
そして、この記事で『フェスバ+』に興味を持ってくださった方は、ぜひ一度ダウンロードして遊んでみてください!僕たちがこだわり抜いた「爽快感」と「公平性」を、その手で体感していただけたら最高です。
コロプラは、これからも面白いゲームを作るために、こうした新しい技術への挑戦を続けていきます。エンタメが好きで、トライアンドエラーを楽しみながら、面白いものを追求していける方、ぜひ一緒に働きましょう!



.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)