.png%3Fw%3D800&w=3840&q=90)
AI記事要約
生成AIが急速に普及し、企業でのAI活用が加速する中、コロプラでは2025年4月、社内におけるAI活用率が約80%*に達しました。
社内でのAI活用推進は、まだ、AIに懐疑的だった2022年頃から始まり、早期から社員へ啓蒙し続けるメンバーの想いや、ひとつひとつの活動の積み重ねがありました。今回、コロプラのAI活用推進の立役者である経営企画本部人事部の石塚秀明さんとCIO室AIイネーブルメントグループの山田和毅さんにインタビューを実施。AI活用推進の舞台裏と、人間の創造性とテクノロジーが共存するコロプラならではのAI活用のあり方について、たっぷりと語ってもらいました。
*社内アンケート回答者のうち、約8割が「業務で生成AIを活用している」と回答

経営企画本部 人事部
- 石塚 秀明
2019年にコロプラに入社し、社内システムの開発を行うインターナルグループを経て人事部へ。現在はテクノロジーで人事課題を解決するHR Techの領域を担い、人事部の業務最適化・効率化に携わりながら、社内のAI活用を推進している。

CIO室 AIイネーブルメントグループ
- 山田 和毅
2017年4月、コロプラに新卒入社。新作タイトルの開発や既存タイトルの運営。技術広報やCOLOPL Tech Blogの運営にも携わる。現在は全社的な業務効率化とエンジニアの生産性向上を目指し、AI活用推進を担う。
コロプラのAI活用の現状とは
石塚さんと山田さんは、コロプラのAI活用推進にどのような立場でかかわっているのでしょうか。

僕は、各部署の業務課題とAI活用に関するあらゆる相談を受け付ける「AI総合相談窓口」のような役割を担っています。また、CursorやClaude Codeの導入サポートをはじめとするエンジニアのAI活用を推進しています。

僕の場合は、現在所属している人事部に加え、「インディツール開発部」という部活動でもAI活用に向けた取り組みを行っています。人事部では、全社的なAI活用カルチャーの醸成や各従業員の知識・知見の向上などを目指し、各種施策を実施しています。インディツール開発部では、ボトムアップで便利なAIツールを考案し、それらを実際に開発して社内に提供。AIを手軽に活用できる環境の整備に貢献しています。
この1~2年ほどで、生成AIが世の中に急速に普及しました。現在の社会の状況を、お二人はどのように捉えていますか?

企業においては、ChatGPTをはじめとしたチャットベースのシンプルな生成AIの導入がかなり進みましたよね。個人での利用も浸透し、最近ではエンジニアでない方々もChatGPTやそのほかの生成AIに詳しくなっている印象があります。

これまでは「生成AI=専門家が使う特別なツール」というイメージがありましたが、最近は日常的に使えるツールとして急激に変化していると感じます。AIに関する情報発信も活発に行われている一方で、社会やツールが変化するスピード感に戸惑いを感じている人も多いのではないでしょうか。

たしかに、AI技術の進化は非常に速くて驚きます。各生成AIのモデルの進化はもちろん、エンジニアが使うAI搭載型の開発ツールもアップデートが目まぐるしく、毎月のように機能の水準や標準的な使い方、使用時のルールなどが変化しています。そうした変革はおもしろくもありつつ、自分自身が今後も変化についていけるのか、少し恐ろしく感じる気持ちもあります。

日々の業務に集中していると、AIに関する新しい情報のキャッチアップがどうしても後回しになりがちです。その結果、AIを使いこなしている人とそうでない人との間にリテラシーの格差が生じてしまう。そのあたりは会社としてもサポートをしていかなければならないと考えています。
コロプラ社内でもAI活用が進んでいます。

そうですね。社内でもこの1〜2年ほどでChatGPTやGeminiの活用が進み、今では約8割の社員が業務で生成AIを活用するまでになりました。特にエンジニアは先端技術への情報感度の高いメンバーが多く、開発ツールを含め、早い段階でAI活用が進んでいった印象があります。こうした現状があるのは、やはり石塚さんが人事部としてさまざまな研修や勉強会などを企画・実施してくださったからだと思います。また、福利厚生で各種AIの利用料金を補助してもらえるのも、AI活用を後押ししているのではないでしょうか。僕は最終的に社内のAI活用率を100%にしていきたいと考えているので、引き続き石塚さんと連携しながら取り組みを遂行していくつもりです。

AI活用率100%は、僕としても目指していきたいところです。ただ、その前段として、現時点で社内の8割がAIを活用している状況を作れたことが、本当にポジティブな成果だと捉えています。高いAI活用率を実現できたのは、AIイネーブルメントグループによる各部署へのAI活用支援があることに加え、我々人事部としても「AI未利用者がつまづいているポイント」を把握し、それを踏まえたサポートを提供できるようになってきているからだと分析しています。僕も引き続き、社内のAI活用を支える取り組みに力を注いでいきたいと思っています。
コロプラとしては、生成AIは今後、ゲーム開発やそのほかの業務において欠かせない存在になると考えているのですか?

そうですね。生成AIは今後、日々の暮らしに欠かせない水道のように、業務にはなくてはならない存在になると思います。
お二人がAIの活用推進に取り組み始めたきっかけを教えてください。

最大のきっかけは、生成AIに対する「不安な気持ち」を解消したいという想いでした。実は僕自身も生成AIの進化の速さに戸惑いを感じていた一人で、SNSなどでAIの活用や新しいツールの情報を得るたびに、「僕はまだそこまでAIを使いこなせていない」と大きな不安を抱えていたんです。そのときふと思ったのが、エンジニア出身の僕でもこうした不安を抱えるのだから、バックオフィスなど非エンジニア部門の人たちも同じようにAIの脅威を感じているのではないかということでした。「このままでは世の中から取り残されてしまう」という焦燥感を、自分も含めたコロプラの全メンバーから取り除きたいと思ったことが、AIの活用推進に携わるようになった理由です。

僕の場合は、生成AIの利用に楽しさを感じたことがきっかけでした。AIを使うと、僕が手を動かすよりも何十倍も速くプロダクトを開発できます。AIでコーディングなどの業務を効率化できれば、これからは人間のリソースを「ゲームをよりおもしろくすること」に割けるようになるはずだと実感。新しい体験を生み出すことに直結するのではないかと思い、AI活用推進を担うようになりました。
「意識せずともAIを使っている状態」をつくる
石塚さんはこれまで、どのような取り組みを手がけてきたのでしょうか。

「学ぶ」「使う」「共有する」の3つのステップで施策を展開してきました。「学ぶ」では、AI初心者向けの研修や「Lunch&Learn」という勉強会を実施。特に後者の勉強会は毎週のように開催し、AIに関する動画コンテンツを見ながらランチをするなどして、継続的なインプットの場を提供してきました。「使う」では、社内のAIチャットボットを有効活用するのに加え、先ほども少しお話したインディツール開発部でのツール開発にも注力しています。
さらに、重点を置いている「共有する」では、社内でAI活用に関する情報交換の機会を多数設けられるよう意識して活動してきました。具体的には、社内コミュニケーションツールのSlackで「はじめてのAI」というチャンネルを設置。AI初心者でもカジュアルに質問したり、発見したことを共有したりできる場を用意しています。また、月1回の頻度で「AIトーク」というトークセッションも行っています。ここでは、さまざまな部署や職種のメンバーが登壇。それぞれのAI活用術をカジュアルに語り合ってもらうことで、社内の他の部署や職種のメンバーの参考になればと考えています。
AIに関する社内のニーズや困りごとは、どのように把握しているのですか?

AI活用に関するアンケートを定期的に実施しており、その中で困りごとなどを書いてもらうようにしています。Slackのチャンネルにも、課題や悩みが寄せられるケースは多いですね。
AI活用推進に携わる上で意識していることを教えてください。

最も心がけているのは、「意識せずともAIを使っている状態」を作ることです。そのためにも、勉強会や事例共有会では、大きな成功事例ではなく、誰もが真似しやすいと感じるような小さな成功体験を積極的に発信するようにしています。
石塚さんは、新たな福利厚生制度「カフェテリアプラン」でのAI活用にも携わったそうですね。

そうなんです。カフェテリアプランの導入では、人事担当者が他社サービスの導入検討フェーズにおける情報収集でAIのリサーチ機能を活用したほか、導入後の問い合わせ対応にもGoogle NotebookLMを利用しています。最適なリサーチ方法の検討や、精度の高い問い合わせ対応を実現するためのデータベース構築などについて相談にのる形で関わっていたのですが、どちらの施策も担当者の業務効率化に繋げることができました。
インディツール開発部で開発したツールは、社内の反響はいかがですか?

部の活動として、「くまぱわーあっぷ」と名付けたさまざまなブラウザ拡張機能を開発しているのですが、最も反響があったと感じているのは、ブラウザで開いているWebサイトの情報などをワンクリックで社内のAIチャットボットに送信できる機能です。活用してくれている社員からは、「思考を中断せずAIに相談できるようになった」「わざわざ情報をコピーしたり、ダウンロードしたりしてAIに取り込む必要がなく便利」といった声をもらっており、業務効率化に貢献できていることを実感しています。
.jpg%3Fw%3D400&w=3840&q=75)

気軽に相談しやすい仕組みを作り、AIの活用を後押し
山田さんはAIイネーブルメントグループとして、どのようにAI活用を支援しているのでしょうか。

僕の所属チームでは、「AIを使ってできることを増やす」「AIができることを増やす」という2つのミッションを掲げて活動しています。前者では、AIがもたらす価値を最大化するためのサポートを行い、特にゲーム会社ならではの体験づくりに注力しています。後者では、AIが扱えるデータ領域の拡大と、データ活用のための基盤整備を推進しています。冒頭でもお話した通り、AIに関連したあらゆる相談を受け付けており、各部署の課題に対してAIまたはそのほかのシステムで解決できるかを検討し、実装に向けてプロジェクトを進めています。
山田さんのもとに寄せられる相談は、どのような内容が多いですか?

作業の効率化を目指した相談が多いです。これまでには、バックオフィスのワークフローの自動化やルールに基づいた分析などをAIで代替する取り組みを進めてきました。
各部署のAI活用を支援する上で、大切にしていることを教えてください。

気軽に相談しやすい仕組みを作ることでしょうか。AIに詳しいメンバーも交えたSlackチャンネルをつくるなど、相談の窓口を複数用意したことで、これまで以上にAIに関して相談しやすい環境を整えています。また、AIを使える人をさらに増やすべく、学習支援や学びの共有にも力を入れています。先日は開発部門にAIを搭載したコードエディタ「Cursor」を導入し、まずは各エンジニアがAIツールを自由に触って知見をためられる環境を用意しました。コロプラではもともと、CIOの菅井が「あなたの当たり前は誰かの学び」という言葉で情報や学びの共有を促してきましたが、生成AIについてもそうしたカルチャーを浸透させたいと思っています。学びを共有するSlackチャンネルでAIについても気軽に発信できるよう、環境整備に力を入れています。
ブロックチェーンゲーム『Brilliantcrypto』にもAIが導入されていると聞きました。本タイトルでは、どのようにAIを活用しているのでしょうか。

『Brilliantcrypto』は、デジタルの世界でNFT宝石を採掘するゲームです。アプリ内にAIを組み込み、低確率で出現する「名前の付いた宝石」の名称や、宝石に込められた背景ストーリーを考えてもらっています。また、ユーザーにランダムで割り当てられるプロフィールもAIが考案。ユーザーごとに個性を出せるよう、機能化しています。
「コロプラならではのAI活用の特徴」をどのように捉えていますか?

失敗を恐れずにさまざまなことを試しながら、他社には真似できない活用のあり方を目指しているように思います。その一例が、今年5月にリリースした『神魔狩りのツクヨミ』。これは画像生成AIをゲームに実装した、業界では珍しいタイトルです。生成AIのゲームシステムへの活用はまだ他社が挑戦していない領域で、今後どのようなスタンダードが築かれるのか分からない部分だからこそ、その領域に積極的に挑戦しているのは、新しい体験を生み出し続けてきたコロプラらしさを感じます。

AI活用推進で直面した壁と得られた成果
これまでに直面した壁は、何かありましたか?

AI活用推進のフェーズごとに、大きく2つの壁に直面しました。1つ目が、AI活用推進に取り組み始めた頃のハードルで、純粋に「AIの使い方が分からない」という認知の壁がありました。この課題に関しては、研修会や情報共有会を開催したことで、現在では乗り越えることができています。2つ目は、AIに対する知識をある程度獲得できたものの、今度は「本当にAIは業務に役立つのか」とメリットやリスクを慎重に見極める社員が増えてきたことです。リスクへの懸念は当然のものですが、AIは正しく使えば業務効率化に大きく役立つツールです。その点をしっかりと伝えつつ、職種によってAIの最適な使い方は異なるため、職種別の事例共有会などもこれから開催を増やしていきたいと考えています。

僕がハードルに感じたのは、社内のAIに対する解像度を上げることでした。取り組みを始めた当初は、解決したい業務課題として、そもそもAIでは実現できないことを相談されるケースも多かったんです。ですが、情報発信や学習環境の整備を行ってからは、そうした相談は少しずつ減ってきました。ただ、まだ課題は残されています。AIで解決できない業務課題は他の仕組みやシステムで解決を目指したり、一部工程でのAI導入を検討したりしながら、引き続き社内のAIへの解像度向上を目指して活動を続けています。
生成AIは、一部のツールで入力したデータが機械学習に使われてしまうそうですね。情報漏えいなどのリスクヘッジは、どのように対策をとっているのでしょうか。

部署の垣根を超えて、全社的なAIの利用ガイドラインを策定しています。おっしゃる通り、ツールごとにモデルの学習へのデータ使用状況は異なるため、各ツールのポリシーを確認しながら、どこまでの情報であれば入力していいのか、AIをより安全に使えるような判断基準をまとめています。
これまでの取り組みで成果を感じているものはありますか?

各チームから相談を受け、多くの人手と工数がかかっていた業務を効率化し、コスト削減に貢献できたことは非常に手応えを感じています。また、開発部門への「Cursor」導入によって、AI開発ツールに関する社内メンバーの発信が明らかに増えた実感があり、この施策もエンジニアチームのAI理解促進につながったのではないかと思っています。

たしかに、社員同士の情報共有は目に見えて増えていますよね。僕もその変化は大きな手応えを感じているポイントです。「AIトーク」などのイベント開催前後でも、社内のあちこちでAIに関する話題を耳にするようになりました。AIツールを使うことが当たり前の文化となってきている一方で、最近、1つだけ困っていることがあります。僕のもとに集まる相談内容のレベルが難化しているんです。それはつまり、社内のAIに対する理解度が高まっているということですから、嬉しい状況である反面、僕自身もさらにAI活用のステージを上げていかなければならないと感じています。
他部署を巻き込んでそうした成果が出せた秘訣や、他部門とのコミュニケーションで大切にしていることがあれば、お聞かせください。

さまざまな施策を通して、日々の業務が忙しくて学習機会を得られなかったり、AIに関して周囲の人と積極的に話して良いのか判断がつきかねていたりした社員の背中を押してあげられた。その結果が、現在のAI活用率80%という数字につながっているのではないでしょうか。

他部署とのコミュニケーションでは、テキストだけでなく、対話をすることも重要です。特に業務課題の解決を目指す際は、こちらが課題の内容や業務に関する理解を深めることも欠かせません。Slackなどでやりとりをしているだけでは分からないニュアンスを把握するためには、打ち合わせを行ったり、担当者の席に僕が赴いて少し話をしたりと、人対人のコミュニケーションが大切だと感じます。

クリエイターの創造性を引き出すAI活用を目指して
今後の展望をお聞かせください。

AIイネーブルメントグループの活動コンセプトに従い、今後も「AI“が”できること」と「AI“で”できること」を増やしていきたいです。前者では現在、社内でAIがアクセス可能なデータや環境を増やすために、ConfluenceやSlack、Googleドキュメントなどを一気に検索可能な「Google Agentspace」を試験運用しているところです。後者では、新しいAIツールを社内で積極的に試すことで、AIを使って何ができ、何ができないのかを確かめ、有効な知見を全社的に蓄積できればと考えています。

僕は部活動と人事部の両軸で、今後もAI活用推進に貢献していきたいです。インディツール開発部の活動では、AIの活用を効率化できるツールの開発に引き続き挑んでいきたいと思っています。また、コロプラではAIポリシーを定め、その中でAIなどに関する「ナレッジシェアの促進」を掲げています。社内にはエンジニアやデザイナーなど、さまざまな専門性を持ったクリエイターが所属していますから、今後も彼らがAIを実際の業務の中でパートナーとして活用し、人間ならではのクリエイティビティを発揮できるよう、人事部として研修や座談会などの施策を実施していきたいです。
どのようなAI活用の形がコロプラらしいと思いますか?

AI活用の形には、いくつかのレベル感があると考えています。コロプラとして最低限、達成したいのが、全社員が日常的にChatGPTやGeminiに業務の相談をし、その結果として多少なりとも業務の効率化が叶うという状態です。この状況が作れれば、複数の生成AIを組み合わせて使ったり、業務フローの中にAIを組み込んだりと、さらにステップアップした活用が可能になると思います。さらに突き詰めれば、最終的にはゲームをより一層おもしろくさせる選択肢のひとつとして、ゲーム開発やゲームシステムの中でAIを当たり前に活用する未来もやってくるのではないでしょうか。

生成AIはあくまでも「クリエイターの創造性を支えるツール」だと思っています。ゲームを生み出す現場において、AIはあくまでも黒子であり、主役は社員一人ひとりです。従来は人手がかかっていた単純作業をAIで効率化し、人間はより創造的な仕事に打ち込む。その結果、日常をより楽しく、素晴らしく彩ってくれるようなおもしろいゲームをつくることができたら、それはとてもコロプラらしいAIの使い方と言えるのではないでしょうか。また、AIを使えば、バックオフィスも含めた全社員がクリエイターとして未知の体験を生み出すことも夢ではありません。AIを上手く活用しながら職種の壁をなくし、会社として一丸となって、多くの方に新しい体験を届けていく。そんなAI活用の形がコロプラらしいのではないかと思います。
最近は「生成AIが人間の仕事を奪う」という話もよく耳にしますが、コロプラでは「人間だからこそできること」に目を向けながら、AIの活用を推進しているのだと感じました。

そうですね。会社のスタンスとして、AI活用を最大の目的に据えないという部分はあると思います。AI先行で物事を考えてしまうと、AIができることの範囲内で施策を検討したり、課題解決を試行したりしてしまいますが、我々がやりたいのはそうしたことではありません。コロプラとして大切にしたいのは、あくまでも「作品を生み出すクリエイターの感性や発想」であり、中心に据えるべきは解決を目指す課題の内容です。そうした考え方がベースにあるからこそ、AIと共存した仕事の仕方を模索することができているのだと思います。


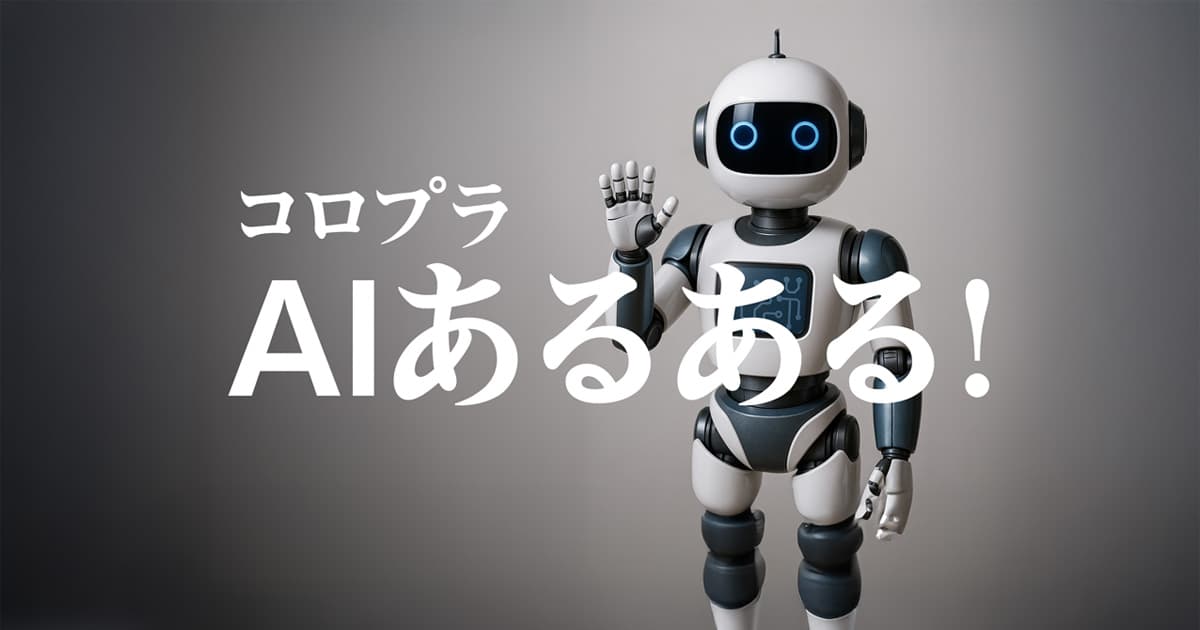
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)