【役員対談】CIO・CDOが語る、ゲーム業界転換期における技術革新への取り組み

AI記事要約
目次
コロプラの手がけるゲームは、時代や社会の変遷とテクノロジーの発展に伴って、大きな進化を遂げてきました。サーバーなどのインフラからグラフィックスなどのUXまで、各分野で新しい技術を取り入れながら、ユーザーさまに新しくおもしろい体験をお届けできるよう、ゲーム開発に挑み続けています。
しかし近年、ゲーム業界の市場環境は大きく変化。生成AIの大躍進とグローバル競争の激化により、国内のゲーム業界は大転換期を迎えています。そうした環境において、コロプラのゲーム開発チームは、昨今の技術的なトレンドをどう捉えているのか。また、中期経営方針を実現させるために、技術領域ではどのような工夫をしているのか。コロプラがこれまで挑戦してきたプロジェクト事例や今後の展望なども踏まえながら、コロプラのゲーム開発を支える上席執行役員2名に話を聞きました。
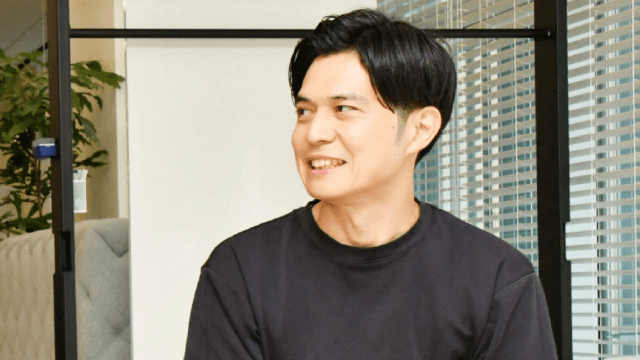
上席執行役員 CIO(Chief Information Officer)
- 菅井 健太
2010年6月にサーバーサイドエンジニアとしてコロプラに入社。アプリケーション開発を担う。その後、ディレクターとして事業開発に従事。また、同時期に、サーバーの問題解決に取り組む社内横断プロジェクトの立ち上げにも携わる。2024年12月より現職。現在はサーバーやファイルインフラなどゲームの土台となる部分を管掌しながら、AI活用の推進にも従事している。

上席執行役員 CDO(Chief Development Officer)
- 池田 洋一
大手コンシューマーゲーム会社でエンジニアとしてゲーム開発に携わった後、2012年12月にコロプラに中途入社。技術開発のエンジニアとして、複数タイトルの開発に携わり、ディレクターも務める。2024年12月より現職。ユーザー体験を司る部分のアプリケーション開発や3Dグラフィックスの構築、技術研究・開発などを管掌。
AI活用は当たり前になるか。ゲーム業界の技術的なトレンドとは
CIOとしてコロプラの技術基盤を担う菅井さんと、CDOとしてクリエイティブ開発を統括する池田さん。お二人は、昨今のゲーム業界の技術的なトレンドをどのように捉えていますか?

生成AIの進化は、やはり目覚ましいものがあります。AIツールの登場によってコードを一瞬で作成できるようになり、プログラミングの知識が乏しい人でも手軽にプロトタイプを作れるようになりました。プログラムやシステムを完成させるまでの時間が圧縮され、市場のお客様に製品・サービスをいち早く届けられる時代になったと感じています。

AIを使うと、開発スピードは各段に上がりますよね。ただ、AIにすべてを任せられるかというとそうではなく、AIが出力したアウトプットはやはり多少なりとも調整してあげる必要があると思います。学習データの量がしっかりと確保されており、ルールが明確に定まっているものであれば、AIに業務を任せられるケースも増えていますが、そうではない領域では、まだ人間の力が必要です。例えば、3DCGのアニメーション制作で考えると、人間のCGアニメーションは膨大なデータがあり、動きをつける際のルールも関節の可動域などによって細かく定まっているものの、それでも現状ではAIに完全に任せることはできません。将来的にはこうした条件が揃った人間の描写なら、AIで制作できる時代が来るかもしれませんね。一方で、学習データが少なかったり、動きのルールを定めにくかったりする犬や猫、馬などの四足歩行の動物のアニメーション制作は、AIにとってまだ苦手な領域です。

ゲーム業界のエンジニアにとって、業務内でのAI活用は当然のものとなりつつあります。AIを使って業務を効率化した上で、自分たちが作るプロダクトの質をいかに高めていくかが求められているように思います。

そうですね。AIでプロダクトの質を高めると同時に、開発スピードを上げ、逆に開発コストは下げていく。そうしたトレンドが、今後のゲーム開発において一般的になっていくのではないでしょうか。

AI活用が当たり前の社会では、エンジニアに求められる知識やスキルはさらに高度化すると考えています。例えば、セキュリティの部分。プログラミングの知識があまりない方々でもプロダクトをリリースできるようになったからこそ、セキュリティの脆弱性の問題がいずれ浮上してくるでしょう。すると、今後はエンジニアがセキュリティの強化など、より深い知識やスキルが求められる部分で仕事を担うようになるはずです。エンジニアとして求められる能力のベクトルは、これから段々と変わってくると思います。
AI以外の技術領域については、何か感じている変化などはありますか?

モバイルゲームの3DCGで言えば、ここ5年ほどでかなり大きな進化を遂げました。ですが、最近はその波が止まってしまっています。なぜなら、3DCGの技術進化の速度が、携帯端末の進化の速度を超えてしまったからです。今実現できる最先端の技術を総動員してゲーム画面を作り込むと、ユーザーさまのスマートフォンのバッテリーや熱を排出する機構がもちません。そのため、コロプラの目指す方向としてはある程度グラフィックス技術に力を入れたので今は新しいグラフィックスを追求するよりも、現在のスマートフォンのスペックの中で、「いかに負荷を下げながら高いクオリティの表現を実現するか」ということに重きが置かれています。

インフラは、現在はクラウドサービスの進化にともなってゲーム業界の各企業で技術的な差異がなくなってきています。大量のアクセスがあっても“落ちないサーバー”の実現が容易になり、今はどのモバイルゲームをプレイしても快適に遊べる環境が整っています。それはつまり、インフラの設計・構築の技術力で競合優位性を確保することが難しくなってきたということ。「遊んでいる最中にゲームに接続できなくなる」といった事態を防げる企業が多くなってきたため、コロプラの強みである「大規模アクセスにも耐えられる技術」が競合他社との差別化を図る要素になりにくくなってきていると感じます。
海外での安定したサービス提供を支える技術
中期経営方針では、「海外市場への積極的展開」「国内IPの活用」「新しいUXの提供」を掲げています。これらの戦略を実行する上で、技術・クリエイティブの観点から方針や考え方があればお聞かせください。

海外展開を進める上では、「多種多様な携帯電話端末への対応」を意識することが欠かせません。例えば、東南アジア地域でよく使われているスマートフォンは、日本や欧米で使われている端末よりもスペックが低いことが多いのですが、そうした端末でも快適に遊んでいただけるよう、ゲームアプリの環境を整える必要があります。
具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。

ユーザーさまがゲームアプリを初めて起動した際、アプリ側で端末のスペック情報を調べ、その内容に合わせてゲーム内の各種オプションを自動設定しています。PCゲームでよく使われている手法をスマートフォンゲームに応用した形です。
多種多様な携帯電話端末に対応する技術は、コロプラの強みのひとつと考えて良いのでしょうか?

そうですね。モバイルゲーム業界の中では他社よりも先行した技術力があると自負しています。
その特徴をより深くご理解いただくために、少しだけ設計・開発思想に触れると、コロプラでは現在、一般的な「オブジェクト指向」に加え、「データ指向」も導入しながらゲーム開発を進めています。
オブジェクト指向とは、システム内の様々な要素を、特定の役割を持つ「オブジェクト」として定義した上で、それらを組み合わせてシステム全体を構築していく考え方のことです。例えば、自動車を“完成したシステム”だと捉えると、タイヤやドア、エンジンなど各パーツが「オブジェクト」です。パーツが組み合わさることで、自動車が動く、つまりシステムが動きます。
一方、データ指向は、その名の通り「データ」に着目してシステムを開発する考え方。データをメモリにどう配置するか、データをどう読み込み、書き出すかという部分に重きを置いて設計・開発を進めます。これはいうなればライン工場のような開発の仕方で、製造ラインに1つのモノを流し、それに加工を施していくことで、1つのパーツを素早く作るというイメージの内部処理を実現させるのです。
こうしたデータ指向の開発スタイルを、最近ではスマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク(以下、ドラクエウォーク)』で取り入れました。ドラクエウォークでは画面内に大量の木のグラフィックスがあるのですが、これをUnityにおいて一般的な方法で作ってしまうと、かなり大きな処理負荷が携帯端末にかかってしまい、画面がガクガクしてしまいます。そうした事態を避けるために、コロプラでは木のグラフィックスをデータ指向で開発。このほかにもゲームの各構成要素で最適な開発・設計思想や技術を採用したことで、臨場感のあるグラフィックスと遊びごたえを両立させました。
ドラクエウォークで使用した技術や開発思想は、国内最大級のゲーム開発者向けカンファレンス『CEDEC』でも発表しています。2020年のCEDECでは、コロプラから「ほぼすべての工程でデータ指向を用いて開発したゲーム」について講演しました。こうしたテーマで登壇したモバイルゲームの企業は他になく、コロプラの技術力の高さを世の中に示す貴重な機会となったように思います。
菅井さんの担当領域では、中期経営方針に関してどのような方針があるのでしょうか。

僕も池田と同じように、インフラ技術で海外市場への積極的な展開を支えられればと考えています。各国の通信状況や携帯端末のスペックにしっかりと対応できるよう、データセンターを置く国や地域を戦略的に選んでいきたいですし、ユーザーさまの体験を最大化できるように、これからも基盤技術の開発、検証を進めていきたいと思っています。
生成AIなどを活用した新しい体験を提供しようとすると、サーバーへの負荷も大きくなるのではないでしょうか。新しい体験を支えるために、インフラの観点で意識していることはありますか?

予算を含めたリソース配分のあり方を入念に検討するようにしています。特に生成AIを使ったゲームは、GPUの確保が欠かせません。ですが、GPUは非常に高いものでもあるため、プロジェクトの予算やクラウドベンダーの供給状況などを見ながら、どのようなGPUを使うべきかを戦略的に考えるようにしています。

コロプラのクリエイティブ表現やインフラ技術の進化に迫る
グラフィックス技術やクリエイティブ表現において、コロプラはどのように進化してきたのですか?

コロプラは、ゲーム業界の中で他社に先駆けてスマートフォンゲーム市場に参入した後、2Dゲームが主流だった中で、3Dグラフィックスにいち早く挑戦してきました。日本のモバイルゲーム開発企業の中では、本当に多様な3D技術にチャレンジしてきたと言えます。例えば、『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』では、3D表現を取り入れたステージを作り、2Dゲームでありながらも奥行き感があるグラフィックスに挑戦したり、『白猫プロジェクト』では本格的な3DCGのアニメーションやエフェクトに挑戦したりしてきました。こうしたチャレンジがベースとなって、最近では「光」の表現も精度が上がっており、クリエイティブ表現の様々な部分で技術やノウハウを蓄積できていると感じています。
インフラやシステム基盤の観点では、コロプラの技術や開発環境はどのように進化してきたのでしょうか。

私が入社した2010年は、まだクラウドが一般的なものではない時代でした。当時は自社でサーバーを購入し、ユーザーさまのゲームへのアクセス数が最大になる瞬間を想定しながら、大きな負荷に耐えられるようなサーバーを構成していました。AWSやGoogle Cloudなどのクラウドサービスが進化する中で、コロプラも徐々にクラウドを導入。サービス事業者と二人三脚で、クラウドサーバーの性能や関連技術を向上させていった歴史があります。コロプラでは2017年頃に、AWSからGoogle Cloudへ切り替えましたが、Googleの持つ分散データベース技術により、負荷対策にかける工程を大幅に効率化することができました。コロプラが創業当初から大切にしてきた「ノーメンテナンス運用」は位置ゲーが出先で遊べなくなるのは大変不本意であるところから生まれましたが、テクノロジーの進化がより支えてくれるようになりました。
そうした技術的な進化を踏まえ、最新の技術やクリエイティブ表現を導入したことで成功したプロジェクト事例があればお聞かせください。

難しい質問ですね……。というのも、最新のテクノロジーは業界でも前例がないことが多いため、ビジネス的な成功に繋がらないケースも多いんですよ。

2025年5月にリリースしたローグライクゲーム『神魔狩りのツクヨミ(以下、神ツク)』は成功事例と言えるのではないでしょうか。神ツクでは、バトルで使用するカードのイラストを、ゲームクリエイター・金子一馬さんの絵を学習した生成AIで出力しています。ゲームシステムへのAIの活用は業界でもまだあまり例がなく、ユーザーさまの中には賛否が分かれる可能性も想定されたため、さまざまなリスクを覚悟して臨んだプロジェクトでした。ですが、ふたを開けてみると、多くのユーザーさまに「コロプラなら何かやってくれるだろう」と期待をかけていただき、楽しんでいただけるタイトルとなっています。

神ツクの成功は、やはり世界観の設計と、生成されたカードをユーザーさま同士で評価し合う投票システムの存在が大きいのだろうと思います。

そうですね。神ツクでは、物語の世界観に沿って、金子さんのようなテイストのイラストをカードに描き出す「AIカネコ」を“偽神”、本物の金子さんを“神”として位置づけています。そうした世界観のもとに生成AIをゲームシステムに取り込んだからこそ、多くのユーザーさまに違和感なく受け止めていただくことができたのだと思います。また、生成されたカードをSNSに投稿することで、金子さん本人から様々な賞をもらえるイベントも行っており、こうした取り組みも神ツクの成功に寄与したのではないかと考えています。
最新テクノロジーを使ったゲームはビジネス的な成功に繋がらないことも多いとのお話でしたが、失敗が続く中でも新しい体験の創出にチャレンジし続けられるのはどうしてだと思いますか?

新しいことにチャレンジし、新しい体験を作り出すことができたら、たとえ商業的には失敗だったとしても、未来につながる試行ができたという意味では「成功」だと捉えているからではないでしょうか。1回の失敗が次の挑戦に繋がることも多く、例えば2013年に発表した『クマのみんなでリバーシ!』というゲームのネットワーク基盤が、2014年リリースの『白猫プロジェクト』の開発に繋がっています。その後、技術を改良して『白猫テニス』のようなリアルタイム性の高い対戦ゲームの開発に繋がり、『白猫テニス』で蓄積した技術が、複数名でリアルタイムにキャラクター同士を対戦させる『フェスバ+』に繋がっています。ひとつひとつの挑戦で失敗点や反省点はあるのですが、その先に次の新しい挑戦が見えてくるからこそ、コロプラは新しい体験を生み出すことをやめないのだと思います。

現在はサービスが終了している、バーチャル空間でキャラクターとコミュニケーションやゲームを楽しむアプリ『ユージェネライブ』も、最大で10万人が同時にゲームに接続できるようにしたり、キャラクターとリアルタイムにコミュニケーションをとれるようにしたりと、様々な技術を培ってきました。これらの技術は社内で捨て置かれているわけではなく、現在も新たなプロジェクトに活用できないか検討や企画を進めているところです。「チャレンジすること」はコロプラならではのカルチャーであり、固有のDNAとして社内に息づいています。




10年後のゲーム業界はさらにオープンな環境になっている?
お二人が管掌されている領域で、現在どのようなことに注力しているのかお聞かせください。

中期経営方針のところでお話したものとほぼ同じなのですが、スマートフォンやPCなど、ゲームをプレイする各環境において、開発速度を上げ、できる限り軽量で快適に遊んでいただけるゲームを開発するという点に力を入れています。

僕の場合は、やはりAIですね。今年は「AIエージェント(※)元年」とも言われていますが、これからは人の作業を自律的に代行できるAIをプロダクトや開発体制の中に組み込んでいくことが当たり前の世界になると思います。ただ、AIにすべてを任せてしまうと誤ったアウトプットが出てくるリスクもあるため、いかに限定的な機能を持たせ、タスクの成功率を上げるかという点に創意工夫を凝らすことが欠かせません。AIをうまく活用しながら、開発の効率性を高め、ユーザーさまに楽しんでいただけるゲームを作っていけるよう今後も試行錯誤を重ねていきたいと思っています。
※AIエージェント:ユーザーに代わって特定の目標を達成できるよう、自律的に計画を立て、タスクを実行し、環境に適応するソフトウェアシステムのこと。従来の生成AIは人の指示を受けて受動的にタスクをこなすが、AIエージェントは能動的に思考し、必要に応じて他のAIモデルや外部ツールと連携し、高度で複雑なタスクを実行できる。
10年後のゲーム業界はどのようになっていると思いますか?

生成AIを使って誰もがプロダクトを作れる時代に突入したので、我々のような一定以上の規模のゲーム会社が開発したタイトルだけでなく、小規模な企業や個人が開発したタイトルも多くの方が遊んでいるような世界観になっているのではないでしょうか。10年後のゲーム業界は、現在よりもさらにオープンなものに変化していると思います。

僕は最近、メガネ型のデバイスに注目しています。AIの進化によってメガネ型デバイスも大きく進化し、最近のデバイスは本当にクリアに映像を見せてくれるんです。デバイスがさらに進化することで、全く新しい体験や遊びが生まれているかもしれません。
現実の延長線上でゲームの世界を楽しめる日が来るかもしれませんね。

そうですね。ただ、そうした「未来の遊び」を実現するためには、たくさんの課題を解決しなければなりません。メガネ型デバイスを装着し、映像を見ている間は手元が見えませんから、手元で何か入力操作などをしなければならないとき、どのように操作を実行するか、方法を考える必要があります。また、メガネ型デバイスでゲームを遊べるようにする場合、道を歩いているときに前方不注意となり、事故につながる可能性もあるため、安全性の担保や法整備をどうするかというハードルもあります。

メガネ型デバイスやVRは、実はコロプラをはじめ、ゲーム業界ではすでにチャレンジの軌跡がある領域です。ただ、かつてはデバイスの進化速度と社会のVR技術の受け入れ状況、有効なビジネスモデルの確立といった条件が整わず、挑戦をやめてしまった企業がほとんどでした。ですが、10年後にはもしかしたら、VRなどが再びトレンドとなっている可能性もあるかもしれませんね。

デバイスも技術も、この10年でかなり進化しましたからね。メガネ型デバイスやVRがこの先の10年でどれほどの進化を遂げるのか、大いに期待したいところです。

技術の観点で言えば、ゲーム業界で生まれた技術を他の分野に応用する取り組みも進んでいます。

そうですね。分かりやすい例で言えば、ドローンの操縦に関連する機器やシステムは、ゲームの操作感を参考に作られているものが多いと聞きます。コロプラとしても、ゲーム技術の可能性を視野をさらに広く持って探っていきたいですね。
そうした見通しを踏まえ、お二人の立場から「今後挑戦したいこと」をお聞かせください。

僕の目標はこれまでと大きく変わりません。作りたいものを、思う存分に作れる組織を目指していきたいと思っています。新しくておもしろい体験をユーザーさまに届け続けるためにも、組織の都合やチームが持つ技術力が、目指すモノづくりの阻害要因となってしまう状況は絶対に避けなければなりません。新しいエンターテインメントを追求し続けられるような組織環境を、これからも作っていきたいと考えています。

AIを活用して業務を効率化し、空いた時間で泥臭くチャレンジすることを今後も続けていきたいです。デバイスがどれほど進化しようとも、ゲームを支える基盤技術でやるべきことは変わりません。「データをいかに収集し、それをどう扱うか」という点に尽きます。データの集め方や管理方法を時代や社会環境に合わせて最適なものに変えていく。この積み重ねの上に新たな体験の創出があるのだと思うため、これからも地道な努力を続けていきたいです。
誰も見たことのない新しい体験を生み出し続ける
業界関係者や株主の皆様、ユーザーさまへのメッセージをお聞かせください。

ビジョンに「最新のテクノロジーと、独創的なアイデアで“新しい体験を届ける」という言葉を掲げているとおり、コロプラはこれからも、誰も見たことのない新しい体験を生み出していけるよう尽力してまいります。これからもぜひ、コロプラに期待し続けていただけたら幸いです。

池田の言葉と近い話にはなりますが、ユーザーさまや株主の皆様、関係者の皆様にはぜひ、コロプラが手がける新しいエンターテインメントを楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。我々も皆様からの期待や応援が大きな励みとなっています。皆様の期待に応えられるよう、これからも新しい価値の創造を追求し続けていきたいと強く思っております。
コロプラでは現在、新卒から中途まで採用活動を強化しています。どのような方に仲間となっていただきたいか、採用候補者の皆様に向けたメッセージをお願いします。

「新しい挑戦」を求めている方と一緒に仕事ができたら嬉しく思います。特に生成AIを使って様々なチャレンジをしてみたいと思っている方には、ぜひコロプラに来ていただきたいです。コロプラでは、社外に表明するAIポリシーはもちろん、従業員がAIを使う際のガイドラインもしっかりと整えています。定められた基準に則ることで、業務の中で安心してAIを使うことが可能です。また、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)でAIの利用料を補助してもらえるため、個人でも業務やプライベートでAIの活用方法をいろいろと試すことができます。AIで未来の可能性をさらに広げていきたいと考えている方にとっては、驚きの環境が待っていると思います。

仲間に加わっていただきたいのは、やはり「作りたいものがある方」でしょうか。ユーザーさまに届ける体験の中身や価値にこだわってモノづくりと向き合える方ですと、コロプラのカルチャーや価値観に深くマッチするのではないかと思います。AIを使えば、誰でもプログラムを作り、アプリをリリースできる時代に突入したからこそ、これからは自分の考えや意思をしっかりと持つことが重要です。新しくおもしろい体験を世の中に届けたい。その想いがモチベーションになって、自ら主体的に様々なことに挑戦し、試行錯誤を重ねられる方と一緒にまだ誰も見たことがないエンターテインメントを生み出すことができたら嬉しいです。皆様のご応募をお待ちしております。
インタビュー・執筆
市岡 光子


.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
