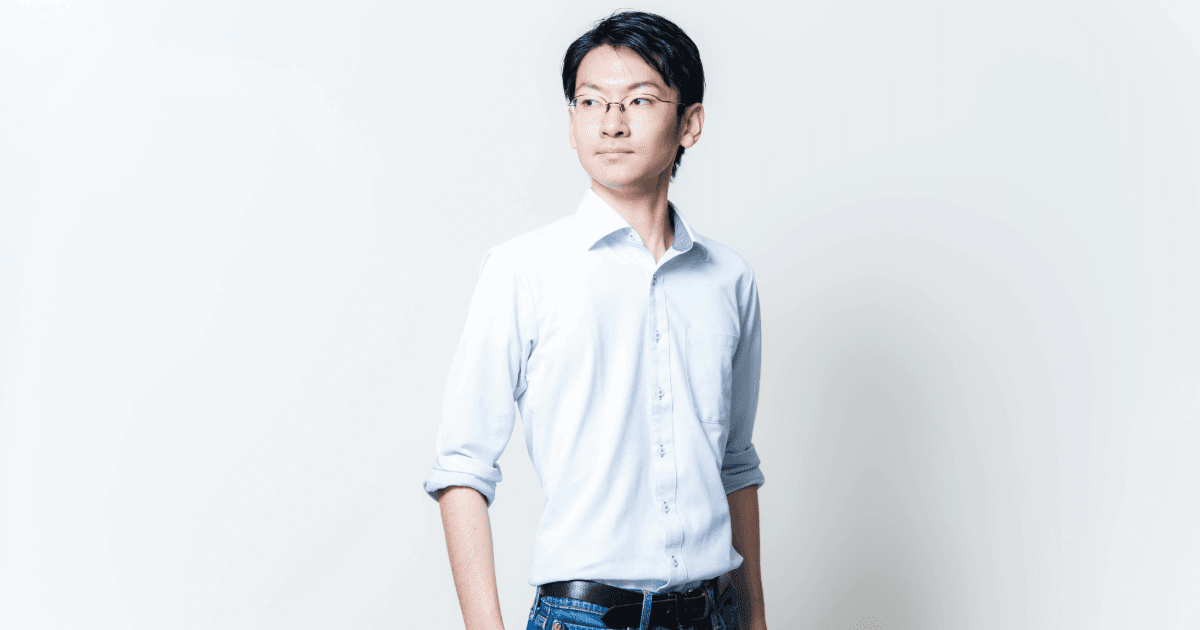新卒研修レポ!見えないところでユーザー体験を支える【サーバーサイドエンジニア編】

AI記事要約
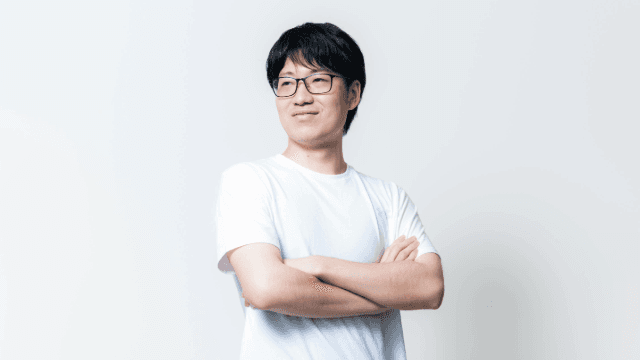
2025年入社 技術基盤本部 第3バックエンドエンジニア部 サーバーサイドエンジニア
- N.K.
MBTI性格タイプ:提唱者(INFJ)
趣味はゲーム、映画・アニメ、小説などです。ゲームはスマブラが好きで、全キャラVIP入りしてます。映画や小説に関してはSFやミステリー系統を良く観ます。最近はリアル体験型の脱出ゲームにハマってます。
はじめまして。サーバーサイドエンジニアのK.Nです。今年の4月に新卒として入社し、現在はとある運用タイトルに配属され、周年イベントの機能開発をしています。
本稿では、私が配属前に受講した「職種別研修」で何を感じ、何を学んだのか。そして、その学びが現在の業務にどう繋がっているのかをお話しします。
職種別研修について
4月の全社共通研修、5月からのゲーム開発研修(Unity実習)、Prizm研修(リアルタイム通信フレームワーク)を経て、職種別研修が始まりました。
サーバーサイドエンジニアの研修は、大きく分けて「サーバーサイドエンジニア向けの座学」と「システム開発研修」の二本柱で構成されています。ここでは、その概要についてご紹介します。
「サーバーサイドエンジニア向けの座学」の内容
- コロプラサーバーエンジニアとは
- オンラインゲームのシステム全体像
- DBについての 基礎説明(MySQL編)
- DBについての 基礎説明(Spanner編)
- ソフトウェアアーキテクチャを学ぶ
- 安全なWebサイトの 作り方
また、「システム開発研修」ではLaravelを用いたWebアプリケーションの開発を行いました。
テーマとしては、コロプラが採用しているカフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)である「miive」の有効活用を促進するような社内システムの企画・開発でした。
まず、社内でヒアリングを行い、社員がmiiveを活用する上での課題やニーズとそのターゲットを分析して企画案を考え、メンターの方にフィードバックをもらいながらブラッシュアップして、作成するシステムを決定しました。
そこから、システムの要件定義や設計、開発スケジュールの策定を行い、システム開発を行いました。
研修での学びと発見
今回の研修では、サーバーサイドエンジニアとして働く上での心構えから、コロプラで使用されている具体的な技術、そして開発実践に至るまで、多岐にわたる学びを得ることができました。
まずマインド面では、「コロプラのSEとは」の講義を通じて、働く上でのマインドセットを学びました。サーバーサイドエンジニアは、ユーザーの目に見えない部分を担うため、一見するとユーザーとの距離が遠いと思われがちですが、実際にはユーザーのプレイデータに直接触れる、ある種「最もユーザーに近い存在」であるという話を聞きました。この視点は、自分にとって大きな発見であり、サーバーサイドエンジニアならではのプロダクト貢献の仕方のイメージが強く持てるようになった瞬間でした。
また、全社共通研修にて、「新しい体験をユーザーに届ける」という目的を強く意識していることを学びましたが、サーバーサイドにおいてもユーザーファーストの考え方が重視されていて、プロダクトにあわせた技術選定や技術ドリブンになりすぎないようになど、根底にある「ユーザー体験」という目的を大切にするというマインドを学びました。
次に技術面では、コロプラで使用されている技術や、基礎的なエンジニアリングの知識を学び、実務に取り組む前の土台を整えることができました。その中で、自分の理解が曖昧な分野を再確認することができ、学びを深める貴重な機会となりました。また、講義後に講師の方へ直接質問させていただいたり、同期と一緒に講義を振り返って議論したりすることで、より一層学びを深めることができ、初めて触れる技術(Spannerなど)の理解もスムーズに行うことができたと感じています。
そして、システム開発研修では、実際にユーザーに使ってもらえるようなサービスに仕上げることの難しさを学びました。というのも、企画当初はmiiveの導入目的の一つである、「部門を超えた社員同士のコミュニケーションの促進」を達成するというコンセプトに気を取られるがあまりに、社員が気軽に使えるものになっていませんでした(他部門の人と関わるハードルがネックになっていた)。そこに対してメンターの方からフィードバックをもらい、部門を超えたコミュニケーションにこだわりすぎず、部門内やよりカジュアルな用途でサービスを使ってもらって、最終的にコンセプトである目的を達成できればいいのではないかという意見をいただきました。それらの意見を取り入れた結果として、より社員が使っているイメージが想像できるような、まさにユーザーファーストなサービス開発ができたと感じています。
職種別研修で現在の業務に役立っていること
研修にて、実際の開発現場で使われている技術の基礎を学べたことは、配属後の業務理解を大いに助けてくれました。 技術的な素地ができていた分、プロジェクト固有のルールやドメイン知識といった、より実践的な内容の吸収にスムーズに入ることができたと感じています。配属後は覚えるべきことが多岐にわたりますが、事前に技術の全体像を掴めているか否かで、吸収の速さに大きな差が生まれることを改めて実感しました。
また、サーバーサイドエンジニアとしてどのように価値発揮して何を成し遂げるべきかという目的が明確になったことも、研修での大きな収穫でした。まだ配属されたばかりで、目の前のタスクと根底にある目的をどう紐づけていくかはまだ模索中ではありますが、頻繁にメンターの方や人事担当者の方との相談の機会が設けられているので、その中でどんどん働き方の解像度を高めていけたらいいなと思います。
今後の抱負
システム開発研修で学んだ「作り手の理想が、必ずしもユーザーの喜びに直結するわけではない」という教訓は、これからのエンジニア人生における、私の揺るぎないマインドセットになると思います。これはゲーム開発においても、常に心に留めておくべきことだと感じています。
また、近年のAIの進化をはじめ、ソフトウェア開発の世界は目まぐるしく変化しています。その激しい変化の波にただ順応するだけでなく、研修で学んだ「ユーザー体験の核心はどこにあるのかを問い続ける姿勢」を軸足として、しっかりと持ち続けたいです。そして、新しい技術を自らの力として、まだ見ぬ「新しい体験」をユーザーに届けるために、成長を続けていきたいと思います。